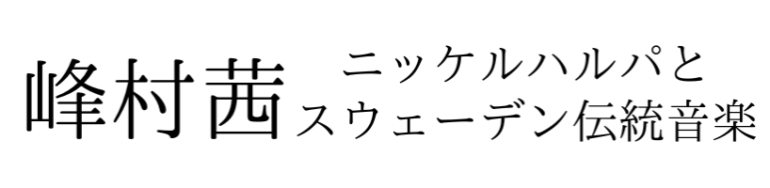以前も書いた『家守綺譚』という私の好きな本について。
この前「ゆっくり再読します」と書いて以来、本当にのんびりのらりくらりと読んできたので昨日やっと読み終わりました。
その中で好きな場面がいくつもあるのですが、2つ引用します。
場面:家にいる主人公、とある事情で池の上をおおうような大きな「網」が必要になった。たまたま家に来た大学時代の後輩の山内君に相談すると、大学のOB会でたまにテニス部のコートを借りることがあり、そのテニス部の人にテニスの「古いネット」を借りてはどうかと提案される。
――しかしいくら古いといって、貧乏学生の寄り集まりの学校だ、そうおいそれと貸してはくれまいよ。
――それが、最近子爵の令息が入ったんで羽振りがいいんですよ、あそこは。
――なんでそんなやつが。
――さあ。馬鹿じゃないことは確かですね。
――ふん。
金もないのに気概だけは盛んなところが我々の共通点である。
場面:知らない老人が釣りをしているところを見かける主人公。「見慣れない顔だなあ」と思い、隣家のおかみさんにその老人のことを訊ねると、「それは人間の姿になりすましたカワウソだ」という。「もし近づいてだまされたら、魚がいっぱい釣れるまではカワウソのそばでぼうっとさせられる(釣りの連れが欲しいから)」らしい。その夜、主人公が夕飯を作ろうとお勝手(台所)に行くと、新鮮な鮎が数匹置かれていた。カワウソの仕業だ。
次の朝、いつものように家の前の道を掃いていたおかみさんに、鮎の話をすると、ひえっと、露骨に禍々(まがまが)しいことを聞いたような顔をされた。
――それで、まだ食べてないんですね。
――はあ、まだです。
――それは不幸中の幸い。きっと、カワウソに、同類と見込まれたんですよ。大変だ。またきますよ。取り憑かれたら、一生、カワウソ暮らしだ。
実を云うと、私はこのとき、その「カワウソ暮らし」という語に激しく引かれる気持ちと、おかみさんの云うとおり、大変だ、という気持ちの二つを同時に感じたのだった。
だそうです。おもしろいです。
物語は短編連作ですが、それでも「サザンカ」の章(タイトルが花や樹の名前です)以降はひと息にたたみかけるような感じがあり、それが最後の「葡萄」の章できれいに落ち着きます。なるほど、という感じです。
亡くなった親友が床の間の掛け軸から頻繁に出てくるなど、淡々としていてユーモラスで飄々としている雰囲気の作品ですが、それでも親友は亡くなっていて(おそらく事件や事故ではない)、主人公は生きています。そこに境界線はあります。
そして主人公は物書きで、あらゆることを言葉で表現したいと考えています。そこに、主人公にとっての喜びがあります。
結局は、「生きる」ということに物語が帰結しているような気がするのですが、どうでしょう。人によって読み方は違うと思いますが。
この主人公だから、親友をはじめあらゆる不思議な存在が目の前に現れたのだろうなと思います。否定せず、ただ見とめて、書くから。失われていく存在が、書かれていくことで、残っていくのです。
今日もお読みいただき、ありがとうございました!
198.曲目は「Grannens bastu」です!もとは歌なのですが、今日はどうしても弾きたい曲が思い浮かばない(思い浮かぶのが難しい曲ばかりで弾けない)ので、いつもよく歌うこちらの歌を弾きました。